
ベンチャー企業としての上場準備や上場を見据えた際の事前に意識しておくべきことをお話をします。今回の動画では、上場後必要となってくる開示体制についてやそれまでにどのような形で準備をするのか、についてお話します。※ベンチャー経営実務編は、ベンチャー企業のCFOや管理部長や実務担当者向けの内容になっています。
上田祐司
株式会社ガイアックス 代表執行役
ガイアックスでは、「人と人をつなげる」をミッションに、ソーシャルメディアとシェアリングエコノミー事業を展開。また起業家が集うスタートアップスタジオという側面も持ち、社会課題を解決するための事業づくりサポート、投資を行う。シェアリングエコノミー協会代表理事。
公式サイト: https://yujiueda.com/blog
Twitter: @yujiyuji
松田光希
アディッシュ 取締役
2015年4月に株式会社ガイアックス入社後、経営管理部M&A担当を経て子会社GXインキュベートを設立、代表取締役社長に就任。シード出資を多数実行した後、2018年9月よりアディッシュ株式会社へ参画し、2020年3月の東証マザーズへの株式公開を推進。2021年1月より取締役執行役員経営企画本部長(現任)。北海道大学理学部卒。
公式サイト: http://adish.co.jp
Twitter: @Mitsuki_2nd
岩本忠史
ガイアックス 経営管理部長
大学卒業後、飲食チェーンのバックオフィス部門勤務を経て、2003年12月ガイアックス入社。財務担当としてガイアックスグループの資金調達や財務戦略の立案・実行、及び数々の出資先の資金調達支援に携わる。株式会社ガイアックス経営管理部部長。株式会社アドレス監査役。株式会社TRUSTDOCK監査役。上智大学経済学部卒。
開示体制。
開示体制。
経理にも絡んでくるのですが 若干また違うと思うので、報告書作ったりとか、この辺りはどうですかね?
経理部長そのものも 採用するの難しいって話をしたのですが、その中にも更に2属性あって、中小企業の月次決算から決算書作成 税務申告書まで一通りやった事ありますが、それでも十分ミドルクラスと言うか レベルは高いのですけれど、更にその1個上に上場企業で有価証券報告書 作った事ありますって言うレイヤーがいて、ここはもう、いないよって感じですね 正直言って。
うん。
上場企業の経理担当部員として、有価証券報告書に記載する 注記の元データのお手伝いをしていました、くらいならもちろんいるのですけれど、有価証券報告書全般見てました、とか、一通り注記の書き方わかってます とか言うレイヤーは、日本国内に存在する上場企業の数を考えれば、そんなにマーケットに出てこないって言うのは 想像に難くなくて、となると、ちょっとかんだ事あるけれど パーフェクトでない人を採用して、それもやはり育てるしかない みたいな感じですね。
つまり開示経験がフルではないけれども ちょっとかじった事あるか、中小企業で開示一通りやっていたから 中小企業の経理部長としては問題ないけれども、上場企業の経理部長としてはスキル0を採用して 頑張って社内で育ってもらうか、とかしか実質的に取る選択肢は ないかなと言う気がします。
すごい採用コストかければ上場企業の経理部長とかを 引っ張ってくる事は可能ではあるのですけれども、採用マーケットにおける母集団が少ないので、それを当てにするのは 僕は結構難しいのではないかなと思っています。
これ、実際上場して一般投資家が出て 本当に開示って言うのは意味があると思うのですが、とは言え、未公開の時期から、その体制ができますよっていう証明を しないといけないわけですよね?
はい。
で、未公開の時に 株主に対してどう開示するのかっていう、そういう開示のための仕事と、言わば一の部とか二の部を 作れるかどうかあたりが、ここら辺に連動してくるのかな とは思うのですが。
はい。
そこら辺のちょっと どれぐらい前からどれくらいの事を、実際にアウトプットして 仕上げなければならないとか、それがどれぐらい評価されるとか そういうような話ってどうですか?
これ、完全に私の経験と 見ていた感覚ですけれど、まず開示経験なくても一の部は作れますね 結論から言うと。
これが結構よく勘違いしがちなのですが、有価証券報告書を作った事ある人でないと難しい のではないかみたいな話はあるのですが、基本的に印刷会社と契約して、日本国内だとプロネクサスか宝印刷のどちらかと ほぼ間違いなく契約するのですけれど、もうそのマニュアル通り 各上場会社作っているので、そのマニュアルを 本気で読み込む覚悟があれば、正直、同じもの仕上がってくるかな と言う感じですね。
もちろんレベル感の差はあれど、所謂、上場できるかどうかと言う視点で言えば 作成はできると思います。
ただ、相当の勉強と相当の監査法人からの突っ込みは 覚悟する必要があるって言う。
こういう注記の書き方ではダメだよとか、こういう風に書くというルールがありまして みたいな、とかは、いろいろ監査法人から 突っ込まれるはずなのですが、それを加味してもプロフェッショナルを マーケットから採用よりかは、担当者が頑張る方が 早いかなと言う気はします。
で、どれくらい時間がかかるかは、その人の速度とかにも よると思うのですけれど、でも、n-2から印刷会社のマニュアルを 本気で読み込めば一の部は間に合うと思います。
うん
契約するの自体も 多分、n-2だと思うので印刷会社、
それができれば、未公開時代にしっかり株主に対して開示体制キープする ってそんなにしないですよね?みんな。
しないです。 上場するまでは既存のVCとかに対しては、どちらかと言うと多分 社長とかがやっている月次の株主報告会とか、四半期のKPIこんな感じですみたいなものを やっていると思いますけれど、それとはもう完全に独立して こっちは進めるって言う形です。
そうですよね。って事は実際 一の部とか二の部でちょっと別物だけど練習をして、あとは上場してからの話ですよ ってそういう話?
そうですね 練習と言うか一の部を世の中に出す前に、四半期報告書はトライアルで 上場する前から作らされるのですよ。
作らされるって言う言い方が正しいのか、作ってレビューして頂くと言う言い方が正しい のかわからないのですけれど、まず上場前に上場のための 四半期報告書っていうのが、上場する時期によるのですけれど、申請期は全部必要で
申請期必要なのですね?
申請期は全部必要で 上場後に四半期報告書を出すので、そういう意味で言うと申請期分の3期分は 45日以内に四半期報告書を作る、と言う開示業務を全部一回経験するのですよね。
で、その上場のための四半期報告書 プラス新規上場のための有価証券報告書、所謂、一の部をセットで作るという形になるので、上場するその日までに、四半期かける2ないし3とほぼ有価証券報告書と同じ フォーマットである一の部を経験をすると言う形です。
なるほど、わかりました。
このあたり岩本さん何かコメントあります?
いえ特に大丈夫です。 ほぼほぼ目論見書みたいな。
有価証券届出書ですよね。
有価証券届出書と有価証券、上場一の部は 微妙に違うのですけれど98%同じですね。
有価証券届出書は一の部の頭に 株式発行に関する情報とかが追加されていると言うのと、カラーでグラフが追加される とか、それくらいの差しかないので、そんなには変わらないと言う形ですね。
あと、開示ではないのですけれど、一の部を作るよりも、一の部の裏にあるマザーズの場合提出する、各種説明資料という 恐ろしい審査書類がありまして、正直、これが一番大変ですね。
ジャスダックとか二の部とか 言ったりするのですけれども、各種説明資料と言うのが基本的には 上場審査の本丸と言う形です。
これに全部の内部統制の状況とか 労務管理の状況、社員数の変化とか過去の予実管理とか 予算修正の有無とか全部まとめた資料になって、その中で開示して投資家向けのPRとか、投資家保護のために出すべき情報だけを 抽出したものが上場一の部と言う形なので、各種説明資料は上場一の部の上位交換、ページ数で言うと、150ページとかかな、あると思うのですけれど と言う感じです。
なるほど、ぶっちゃけ どれくらい時間かかります?それ作るのに。
丸一年はかかりますね。
本当に丸一年かかる。 で、データを集めるのがとにかく大変です。
過去数年分の労務の人数推移とかも もうベンチャーだとパッと出てこないので、えっ?いつ1人辞めた?みたいなものとかも わからなかったりするので、そういうデータを 全部集めているとすごい楽です。
うん、どこかのタイミングで 手頃なSaaSを入れて、ちゃんとSaaSで契約継続し続けるとかが ポイントかもしれないですね。
そうです、なるべく初期からもう本当に データ残すって言うだけで全然負荷は変わります。
うん、わかりました。
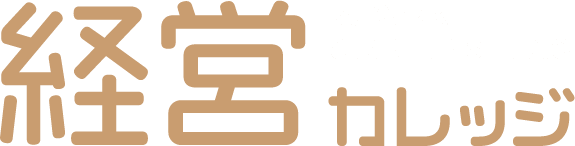


Comments (0)