
事業計画の具体的な作り方についてレクチャーします。何から考え始めればいいのか、どういうツールで作成するのがいいのか、などについてレクチャーします。
目次
上田祐司
株式会社ガイアックス 代表執行役
ガイアックスでは、「人と人をつなげる」をミッションに、ソーシャルメディアとシェアリングエコノミー事業を展開。また起業家が集うスタートアップスタジオという側面も持ち、社会課題を解決するための事業づくりサポート、投資を行う。シェアリングエコノミー協会代表理事。
公式サイト: https://yujiueda.com/blog
Twitter: @yujiyuji
今日は事業計画の具体的な作り方について
事業計画の具体的な作り方
お話をしていきたいなと、思っています。
まず、事業計画ってどういうコンテンツが、あると思いますか?
そうですね。
事業計画だともうどれぐらいの売上で、どれぐらいの利益を出すのかっていう、PLの部分だったりがメインになるかと思います。
そうですね。 他はどうですか?レオさん。
PLの他にもCFが重要だと思っていて、収支で赤字が出ても会社は倒産しないですけれど、資金がショートすると会社が倒産してしまうので、そう言った意味で、大事な指標になってくるかと思います。
二人とも満点回答ですね。
素晴らしい。だいぶわかってきてますね。
事業計画っていう単語も曖昧単語なので、特に正しい定義はないんですけれども、一旦今日話すのはどういう内容かと言うと 数値面に関してですね。
で、数値面で言えば主にPLだったり キャッシュフローだったりって言う、この二つが仕上がりとして重要になってきます。
で、他にも事業計画、この産業における事業の競争力を 作り上げるにはとか、何か組織をどう作るにはとか、そういうのも色々ある。 あるって言うか、事業計画という単語には それを含んでたり含まなかったりするんですが、今回はどちらかというと、狭義の意味の事業計画の、 そして具体的な作り方。
これをどう分析していくのかとかっていうのは また別の回に回させて頂くとして、実際作業として具体的にどう作るのか についてお話できればと思います。
で、これは後々のお話でもしますが、本来重要なのはカテゴリーナンバー1。
別の言い方すると 競合にどう勝つかって事なんですが、それも今回はちょっと対象外と させてもらえたらなと思っています。
事業計画の目的
で、事業計画の目的って言うのは、もうこれ本当 二人の通りで追加する事はないんですが、儲かるのかどうかと、仮に儲かろうが赤字になろうが ともかくキャッシュフローはどうなのか。
結局、ベンチャー企業のあるあるは、お金を突っ込んで ビジネスを作り上げるんですが、そのお金が回るんですか?っていうのを やっぱり確認しなければならない。
だから半分資金繰り表的な、資金繰り表みたいな タイトな話じゃないんですが、2年3年かけてどれくらいファイナンスしますかね みたいなのまで繋げていくって言うのが重要です。
これ前回お話したところでもあるんですが、具体的なところに 今日は入っていきたいと思います。
使用ソフト
まず今時ですけれど 使用ソフトとしては、まぁGoogleスプレッドシートが ベストかなという風に思います。
これは今時のネットベンチャーだったら、G Suite契約して 最近名前変わったのかな?
Googleの企業向けの1アカウント 500円とか1000円とか1500円のものを契約して、スプレッドシートって言うのが 妥当かなと思ってるんですが、ま、これも5年前だと ちょっと機能がプアすぎて、あまりお勧めできなかったんですけれど、今時もう充分ですし、あとやっぱり社内外の共有。
僕もPDFで共有されたりしているんですけれど PDFで共有されてもなぁって言う感じですし、あともう一つは まぁ、これも後々話していきますけれども、事業計画って言うのは 整理的なものじゃなくて、更新とかみんながいじれる って言うのが重要で、そういう意味では 複数人が作業しながら更新できるという意味でも、Googleスプレットシートがベストかな と思っています。
作成時の考える順
作成時の考え方なんですけれども、仕上がりとしてはPL、CFなんですが、考える順番として一番重要なのが まずKPIですね。
KPIって言うのはすごい これもうKPIもうちょっと広い意味で、取って頂きたいんですけれども、KPIって言うのはKGIに対する、それをよく計れるインジケーター と言う事なんですけれども、ま、そこまではいかない。
例えばお客さんに長期滞在ホテルでしてもらいます っていうビジネスをするとしたら、KGIがお客さんの利用回数だとして、KPIがリスト化されたお客さんの数だったり、ホテルの数だったり みたいなところかもしれませんが、もうちょっと広く考えて、その広告を打った時の反応率だったり、1部屋あたりで泊まれる人数だったり、ホテル辺りに何部屋出してくるのが多いのか みたいな数字だったり、ともかくPLでもなく そして経営上気にする数字の事を、今KPIと言う風に、一旦言わしてもらっています。
じゃあ例えばこういうKPI どんな数字があり得ると思います?
そうですね、サイト訪問者数だったり ユーザー登録数だったり、
そうですね。
まあもちろん その購入者数も入ると思います。
その通りですね。いろんな産業で、この産業だったらこういうのが数字でありますかね みたいなそういうのも含めて。
例えばレオさんどうですか?
すみません、わからないんですけれど、1日あたりのユーザー利用数は 違うんでしたっけ?
いえいえ そういう数字でも何でもいいです。
あっ大丈夫。
じゃあ例えば1日あたりの利用ユーザー数 っていうのはPLの科目にあると思います?
ないと思います。
そうですよね。ないですよね。
例えばPVなんかもないですよね、PLに。 キャッシュフローもないですよね。
でも事業計画を作るにあたってはそういった事業上 の数字って言うのが当たり前ですが重要ですね。
で、事業計画のほとんどは、こういった事業上に出てくる数字を ひねくり回すというのが事業計画の基本です。
事業計画を作るからといって PLから作らなくていいです。
PLから作り始めると どうしてもPLの順番、売上だったり原価だったり、その下に販管費があって まず人件費があって、みたいな。
そういう風に落とし込もうとするんですが、それ結構難しくて、なんかこう売上が発生すると どうしても交通費がかかる、みたいな、そういうパターンがあったりするんですが、PLの場所が全然違うので、PLを元に事業計画書こうと思っても なかなか書けないんですよね。
やっぱり事業、事業において、そのいろんな事業に出てくる数字だったり KPIがあると思うんですが、そういったKPIを整理整頓して 数字を書き込んでいく。
もしくはその関連性を整理していくっていうのが 事業計画の作成する時の順番です。
で、そういった数字がPL上どう表現されるのか っていうのは考えればわかりますよ。
例えば中古の服仕入れました。
ま、だいたい中古の服は 壊れているケースがあります。
そういった不良品率、みたいなのを じゃあどうすれば下げていけるのか?
これが結構経営上利益率を上げるために 重要な行動パターンです、と。
で、事業計画では 1年ごとに1ポイントずつ改善していきます。
みたいなそういうのをKPIと言うそのレイヤーの 中でいろいろ組み立てていくんですが、それを最後PLに落とすなんてのは すごい簡単な事なんですよね。
で、もちろんこれ 事業計画を具体的に作り上げるにおいて、例えばアカネさんが今そのワーケーションの サービスをしているとして、頭の中にあるのを紙に落とすのか、紙に落とすことによって頭が整理されるのか これどっちだと思います?
そうですね 後者のイメージがあって、いろいろな変数を動かした時に どういう結果になるのかって、いうのを試せるのかな っていう風に思います。
そうですね、はい。
おそらくKPIとか定数っぽいのは 仮置きで頭の中にあると思うんですよね。
一方でじゃあそれが組み合わさった時、会社として 現実として、利益が何%の利益率で出てくるのか っていうのが頭の中にないと思うので、その定数を動かしながらも調整していく って言うのは重要だと思います。
話は戻りますが KPIを作っていくっていうのが大重要な事です。
で、これ投資を受けるサイドって言うか 投資をするサイドの視点でも、それを見るのが結構重要で、PLを見ても100社投資してください って来た会社の100社が、全てPL上儲かってる形で違ってくるんですよ。 当たり前ですけれど。
赤字で倒産しますっていう事業計画 持って来られないので、みなさん。
絶対儲かりますって言う事業計画 持ってくるので、で、PLを読み取るのって、ま、PLを渡されてももうこっちとしては なんともツッコミようもないし、何ともできないですよね。
むしろKPIとかこういう事業数値を どう組み立てているのかな、みたいな。
例えばホテルの部屋数を増やせば、自ずと売上が上がる という風に思考して作っているのか?
はたまた客さえいればホテルがなくても 売上が作れるという風な思考で考えているのか?
両方ボトルネックだと考えて 両方が満たされると、売上が生まれていくと言う風に 考えているのか?
そういう風な枠組みを投資家としても見るし、それが事業を数字で落とし込んでいるような 形態なんですよね。
だから、PLに落とし込んだからと言って 事業とPLは紐つかないですよね、正直。
で、話戻りますがそのKPIを作ったら PLに展開する事は簡単です。
そしてPLを作ってしまえば キャッシュフローを作ることも簡単です。
ちなみにPLからキャッシュフローって どうやって作るんでしたっけ?
そうですね、PLの中に反映されている その減価償却の部分を引くと、営業キャッシュフローになると思います。
そうですね。PLの利益に 減価償却分を足し込むって事ですよね?
あっ、そうですね、はい。
で、それとは別にすみません PLには表現されてないですけれども、BSに乗っかってくるような投資をしている場合は キャッシュフローから差っ引くと言う事ですよね。
ま、投資キャッシュフローなのかもしれないし、在庫として膨れ上がっていっている かもしれないけれども、PLでは表現されてないけれど BSで資産として乗っかってくる分、キャッシュフローではマイナスのインパクトを 与えるって言う事ですよね。
そういったBS上の資産に乗っかってくる分も KPIを作れば整理できるので、KPIを作ってPLを作る。
で、BSももしかしたら1行2行用意して、それを組み合わせて キャッシュフローを用意するって言う事ですね。
で、キャッシュフローで用意するのは、営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを まず用意します。
なぜかわかりますか?
なぜ、まず 財務キャッシュフローは用意しないのですか?
ちなみに営業キャッシュフローは どんな数字だと思います?
事業立ち上げた前半は。 プラスかマイナスか?
そうですね、立ち上げた前半は まぁプラスじゃないことも多いですかね。
そうですね、立ち上げた前半は 大きなマイナスになる可能性が高いですよね。
まぁベンチャービジネスですから。
投資キャッシュフローはどうですか?
投資は一気に投資をする・・。
そうですね、最初に固定費などに 一気に投資すると思うので、設備などに投資すると思うので マイナスだと思います。
そうですね。
結局、営業キャッシュフローも 投資キャッシュフローも、大きなマイナスなんですよね。
そういったマイナスを どう工面するのかっていうのが、借り入れだったりエクイティ調達だったり つまり財務キャッシュフローなので、まず準備するべきは 営業キャッシュフローと投資キャッシュフロー。
対象期間
では、次の中身に 移っていきたいと思います。
事業計画は基本的に 月次で作るのがスタンダードです。
スプレッドシートの作り方で 右に引けばそのまま、何ヶ月先でも作れるような形態で 作るのが一般的で、1行ずつ計算していく と言うか、1行ずつカスタマイズしていく って言うのは考えられないので、ある方式に従って 計算式で数字ができるようにして、それを右でばっと引っ張れば 未来永劫までできるけれども、まぁ、60ヶ月分ぐらい。
基本的にはエグジットくらいまで作る って言うのが一般的ですね。
続いて年次をどうやって作るかというと、基本的には別のシートを用意して その項目は全部コピーして、で、12ヶ月分の足し算をする。 もしくは最終月を採用する。
例えば現金残高とか顧客数は12ヶ月分足し算すると 変になるので最終月を取ってくる。
例えば売上とかは12ヶ月分足し算する 必要があるので足し算する。
そういった別のシートを作って、つまり11行空で12行目に数字があって、また11行空で12行目に数字があってっていう、その月次のPLの裏にもう1枚ページを作って、ほぼ月次と一緒なんだけれど 足し算して作っていて、で、空白のところは行をまとめるとか 列をまとめるってしたら、足し算、足すマークが出てきて それを押すと閉じられるので、それで作るということですね。
月次でチェックするより年次でチェックした方が 現実的かどうかっていうのはわかりやすいです。
当たり前ですが グラフで見た方がわかり易いんですが、年次のグラフが一番わかり易いです。
さすがにこれはないだろう みたいな事業計画とか、1年目1億赤字ですけれど、2年目から5億利益で 3年目20億利益とか、そんなわけのわからないものも 出てくるんですが、それぐらい変だったら月次見た瞬間に 変だなって思うんですが、年次でまとめているぐらいの方が なんとなく数字感として、めちゃくちゃな事を言ってないよねって事を 確認できるかなと言う気はします。
事業計画の見本
続いてなんですが、今のお話ししたのをスプレッドシートで どう表現しているかって、ざっくり言うとこんな感じですね。
上が月次で並んでいって、左側にKPIがあってPLがあって CFがあるというところです。
事業計画の実物
もっと具体的なシート。
ちょっと字が小さいので 見えないと思うんですけれども、これが具体的なシートのイメージです。
一番上に年月。 例えば2021年3月とかってあって、ま、トピック。 これは別に必要ではないんですが、例えばこの時期に 第2回目のファイナンスをする、とか、第3期がスタートします、とか、そういうトピックを入れたりしますよね。
法律改正があって大きく事業が変わってとか、この日、ここら辺に法律改正の予定とか、そういうのを入れるのも 変じゃないかもしれません。
次、経過月数と経過年数って言うのは 結構使い勝手が良いのでお薦めしています。
事業計画を作る時に 例えば管理部スタッフ2人ぐらいなんだけれど、1年に2人ずつくらい増やす予定って時に、経過月数とか経過年数を 一番上に入れておくと、それを計算式で採用できるので 定数として使い勝手がいいので、経過月数、経過年数というのを よく入れています。
で、次にKPIの群ですね。
これは事業によって全然変わりますが、こんな感じで それぞれのKPIを設定していくって事です。
その下にいくと次PLですね。
PLはだいたい30行だったり 50行だったりすると思うんですが、大枠で言うと 売上、原価、粗利益、販管費、営業利益。
この大枠がこの5つだと思うんですが、これも折りたたむことによって、その5つだけで見たければ折りたたんで、もうちょっと細かいのを見たら拡大させてチェック できるようにすればいいのかなと思います。
で、最後にキャッシュフローのシートは その下に続くという感じになっています。
ここまででご質問ありますか?
大丈夫です。
大丈夫です。
定数の設定
はい、では次に、定数というものを設定すると言うのも これ事業計画では必要で、定数と言っても いろんなカテゴリーの定数があるんですが、まず、固い定数って言うのがあります。 例えば税率、消費税。
消費税が関係する事業計画と 関係しない事業計画があるんですが、例えばそういった消費税を採用する時に、税率、例えば定数というシートを 別に1個作って、そこに税率って書いて 例えば10%って書いて、で、その10%っていうのに名前を付けて、例えばタックスレートみたいな名前を 付けておけば、その名前を他の計算式で 毎回使えるんですよね。
他にも例えば社保の比率。
給料に対して例えば 16%ぐらい社保として見込んでいます。
で、この社保の比率も 例えばそういうような名称を付けておくとか。
こういったものが固い数字ですよね。
で、ここまで固くないけれども 事業毎に変わってくるような定数。
計算式で出してくる KPIみたいなのもありますけれど、その前提となるような数字もこういった形で 定数として設定していてもいいかもしれません。
ま、これも名前を付ける事によって 後で採用できるので、別のシート作って定数は定数でセットして おいた方がいいのかなと言う風には思います。
定数の設定の見本
具体的にはこういう形なんですが、例えばタックスレートって書いてあって データの名前付き範囲ってやれば、そこに名前を付けるので、以後そのつけた名前を 数式内で使っていけるという事ですね。
係数の設定
次にさっきの事業計画の中の係数に関してです。
係数はだいたい二つぐらい あった方がいいかなっていうのと、あと計算上のための空白列っていうのも あった方がいいかなと言う風には思います。
係数の設定の見本
具体的にどういう事かって言うと、これスプレッドシートのイメージなんですが、一番上に係数1、係数2ってありますが、例えば顧客獲得に関しては、突っ込んだ広告宣伝費から係数1 例えばCAC 3万円だとしたら3万円で割ったもの、ただ少なくとも毎月100人は オーガニックで来るからプラス100、それを係数に書いておいて、それが新規獲得の会員数 みたいな感じで書いたりとか、どういう風に係数を使うかわかりませんが、まぁ2行ぐらいあった方が 使い勝手いいのかなと言う風に思います。
そして項目とか係数のすぐ横から、2021年5月、2021年6月ってスタートすると これ後で苦労するので、その間に空白行を必ず1行か2行 入れておいた方がいいです。
例えば具体的には 例えば現金残高、どういう計算式書くかイメージつきます?
前月末の数字+今月の現金増減を足し込んで 今月に書き込みますよね。
翌月もまた前月の残高プラス 今月の増減を足し混んで下に書きますよね。
その時に同じ計算式でいこうと思ったら、1行空けておいてそこにこの事業計画を 書いた瞬間の現金残高を書き込んでおけば、それを足し算の時に引っ張れるので、そこに空白が1行か2行あるかないかで、計算式がそのままコピーできるか、コピーできないのかがかかってくるので 用意しておいた方がいいですね。
これ1行、2行おいておけば それこそ1行目の月を横に引っ張るだけで、永久に事業計画作れるようになっているので。
チェック用シート
で、あとこれもお薦めなのが チェック用のシートですね。
チェック用シートの見本
事業計画とか作っていて 所々合理的に考えて、
これがこうだとダメなんだけどな みたいな事があると思うんですよね。
それをチェックできるようなシートを 別途用意して、例えば、キャパの上限。
いくらなんでも100%超えているとこれ 理論的におかしいみたいなのはチェックしておいて、これがエラー出ていたら ちょっと修正しないと、みたいな。
これは事業によって異なりますが。
こういうのがあると 後で自分でチェックしやすい。
もしくはいろいろ数字を変えた時に 一々チェックしなくて済むのかなとは思います。
これシート名見てもらえればと思うんですが、例えば物件取得コスト。
例えば物件取得がすごいややこしければ それ用に1枚ページを作って、色々そこで計算をして、で、月次のPLを作って 年次のPLも作って横に並んでいます、と。
それとは別にチェックシートがあったりして、ちなみに資本政策とかはその後ですね。
別のスプレッドシートでもいいと思いますが、同じスプレッドシートだとしても それはまた次の話になってくるのかなと思います。
PLの科目の記載
続いてPLの科目ですね。
これもシリーズCとかDとか 上場企業とかになってくると、話はまた違うんですけれども、どうしても財務のコントロールを会計上の数値と 一致させたくなるニーズが強くなってくるので、PLの科目を正しく使う っていう傾向が出てくるんですが、初期フェーズにおいては そこまで気にしなくていいと思います。
つまりどういう事かと言うと、会計的な正式な単語を使わなくていい と言うか、例えばなんですけれども、PLの会計用語としては 業務委託費というのを、使うケースが多いんですが、例えば業務委託費の中に 公認会計士さんへの業務委託だったり、例えば物件を探すために雇った人の 業務委託費だったり、そういったものが業務委託費という中に 入ってくるんですが、事業計画の初期フェーズは PLにそこまで正しい科目を使おうとせずに、物件を探す人への業務委託費 みたいな科目で作っちゃっても、別に構いませんって言う事ですね。
ただ外の人とのコミュニケーションのために、それが原価なのか販管費なのかは、ちょっと整理して書いて おいて欲しいな、みたいな。
そこもぐちゃぐちゃになってくると、外の人とのコミュニケーションが できなくなってくるので。
科目は適当でいいですけれども大きな区分ぐらいは 間違えてない方がいいなと思います。
もしくは、もう科目をきっちり合わせにいって、PLの下の方に業務委託費っていう内訳は 公認会計士への業務委託費。
物件を探す人への業務委託費。
なんとか向けへの業務委託費。
3つを書いて3つの足し算がそこに採用される ような書き方をしてもいいかもしれません。
KPIから下の内訳にいって 内訳が合算として、PLの業務委託にかえって来る って言うような形になります。
作成時の注意点
で、あとは 作成時の注意点なんですけれども、これもすごい基本的なので 是非守って頂きたいんですが、デザインは基本的には入れない方がいいです。
右にざっとやったり いろいろ作業してくると狂ってくるので、できるだけシンプルに 作っていた方がいいです。
線とか空白とか装飾とか 無駄な装飾は不要だと思います。
ただ事業計画も 全部計算式だけで成り立つかって言うと、そんな綺麗なものでもないですし、例えばトピックに合わせて 大きく計算式が変わるところもあるので、そういうところはもう計算式無視し 実数をやっぱり入れにいったりするんですよね。
例えば2022年の3月の時に 社員が毎月1人ずつ増えてくるけれど、新卒採用がスタートするからここから社員が いきなり10名増えちゃいます、みたいな。
その10って言っても計算式やってられないので 手書きで書きにいくと思うんですが、その自分が書き込んだ10という数字と、計算式で出来ているその計算式の 生み出した数字の違いがわかった方がいいので、その書き込んだ10は、例えば黄色の背景つけるとか イタリックにするとか、ちょっと分かりませんが 青文字で作るとか。
自分で書き込んだ数字、実数に関しては 色を変えたりしてした方がいいと思いますが、そうではなく見栄えを良くするために 字を大きくしたり小さくしたりするっていうのは、後で苦労するので やめておいた方がいいかなとは思います。
基本的には皆さん スマホでお仕事していて、スマホビューが必要だと 思われる方もいると思うのですが、事業計画に関しては これはなくても許されるかなと思います。
もう1個これも よくある話なんですけれども、印刷とか全く考慮する必要ないので、なんでこれ こんなに見にくいのかなって思ったら、あっ、印刷をイメージしているのかって。
今時印刷をする人誰もいないので。 印刷は一切無視して。
で、どうしても印刷したいって言うんだったら、ちなみに先頭の行列 例えばPLの科目とか2021年6月とか、そういった科目について 固定する機能があったり、あと長いと印刷した時に 本当に見え辛くなるので、折りたたみ、さっき言った 折りたたみの機能とか使えば、コンパクトになって 印刷もし易くなるかなとは思うんですが、基本的には印刷することはないかな と思います。
印刷とかPDFとかするぐらいだったら、スプレットシートのコピーくれよって言う。
それがもう基本。 スプレットシートの閲覧権限でもいいし。
それをこっちで勝手にコピーして 勝手にいじったりするので。
そういうような形でいいかな と言う風には思います。
なんと非常に細かい話ばかりでしたが、事業計画の具体的な作り方 というところでご説明しました。
実際アカネさんとかも 今作ったりしていると思うんですが、日頃作っている作り方と 何か違う点とかありました?
まさに今は誰かに見せるためって 言うよりは自分のために作っているので、それこそfacebook広告みたいな形で 書いちゃってたりとか、項目を。
自分が何にお金を使っているかを把握するため って思ってやってたんですけれど、それで今はいいのかな って言う風に思いました。
そうですね。 そういう意味ではKPIをいじいじして、PLとかCFを作ってないって感じですよね。
えっと 確かに計画は作ってないですね。
結果だけを作ってます。
あっ、なるほど。
PLの計画はまだなくても いいかもしれないですけれど、KPIあたりはどう関係してるかっていうのは 作ってみてもいいかもしれないですよね。
そうですね なんか初期に作ったんですけれど、あんまり今機能してないので ちょっともう1回見直します。
そうですね。
いつ外部調達になるのかという事が わかるための資料でもある一方で、外部調達が必要になってこない限りは 事業計画なくても事業は進むので、手元に現金あれば。
つい後回し後回しになりますが、それは様子見ながら 作られたらいいかなとは思いますね。
そうですね まさに前回の内容と一緒で、本当に毎週結構計画も変わるフェーズだと思って いるので今精密な計画はしてないですね。
ただKPIは確かに立てて皆が見られる状態には しないといけないなとは思います。
はい、他はどうですか? 何かご質問とかコメント等あれば。
そうですね 質問なんですけれど、上田さんが24歳で ガイアックスを起業された際って、事業計画書ってどういう媒体で、どういう方法で作成していたのかっていうの ちょっと興味がありまして。
当時はマイクロソフトのエクセル というものを使って作ってましたが、まあまあ中身は一緒ですよね。
当時はまだプリントアウト文化だったので、プリントアウトして、同じテーブルでプリントアウトされたPLを 見ながらディスカッションする、みたいな、そんなことがあったんですけれど、ま、正直無駄としか思えないですよね 今時考えれば。
数式見たらわかるだろって言う 数式見せろよ、こらって言う。
そういう感じなので。
僕自身24歳で起業したんですが、22歳で就職して 1年半経営コンサルティングというか、経営情報提供サービスみたいな そういう会社に属していたので、お仕事の中でPLを引きまくっていた。
お客さんに提案するたびに お客さんのPLを代わりに作って、新規事業投資をして 銀行からいくら借り入れて、税金が今本業でこれだけ儲かっていますけれど 新規事業赤字出るので、これだけ節税効果があって、みたいな そんなのを作っていたので、すごく慣れ親しんでいたので、創業直後からパラパラ作ってましたけれど、必ずしもそんな人ばっかり じゃないとは思うので、でもさっき説明したやり方でやっておけば、精度は初めはシンプルでもいいですけれど、その作り方のイメージとしてKPIがあって PLがあってCFがあってっていう、作り方をしておけば思考はすごく整理されるので いいかなとは思いますね。
本当にお恥ずかしながら 事業計画書って、パワポで作るものだと思っていたんですけれど それはもう論外なんですかね?
いや、それが一番最初に言った話でして、そのピッチデッキと言うか そのプレゼン資料はパワポで作ります。
で、その中にPLの計画だったり PLの事業計画だったり、キャッシュフローの事業計画だったり っていうシートが、1枚か2枚か3枚かあると思うんですが、そこの部分はおそらく ハイライトになっていて、このスプレッドシートで作った 事業計画の年次の省略版を、グラフにしてペタッと 貼り付けていると思うんですよね。
そのピッチデッキの事を 事業計画とも言いますし、この今日説明した数字のところだけのところを 事業計画とも言いますけれど、今日はその数字のところだけの ご説明をさせてもらったっていうところです。
プレゼン資料だったり ピッチデッキって言われるものはまた別の機会に、どういう要素を入れて作るべきかって言う お話はできるかなと思います。
ありがとうございます。
何か事業計画の雛形とか ネットによく落ちてたりするんですかね。
そうですね 今日僕がお話したものに関しては、いくつか整合性が取れていない状態 ではあると思うんですが、共有できる範囲で整理して、皆さんがダウンロードできるように しておきたいと思います。
ありがとうございます。
それめちゃくちゃありがたいです。 ありがとうございます。
あともう一つ計画書を作った後に どう使っていくかっていうところで、もし気をつけていた事などあれば。
例えばどういう風に共有してとか どういう頻度で見返してとか、結果も同じシートに 内に作るのかとか、もしあればお伺いしたいです。
はい、それについてはまた では次回と言う事にさせてもらって、今日はこれで終われればなと思います。
はい。
はい、では どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
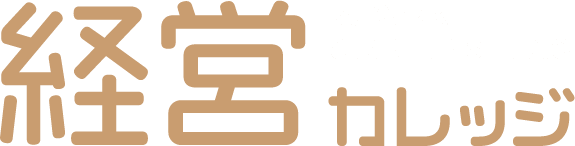

















Comments (0)