
損益分岐点と限界利益まず固定費を下げろ!会計基礎 (7)
固定費と変動費の特徴は何か、会社のフェーズに合わせてそれぞれをどういう割合をどうするのがいいのか、についてレクチャーします。また限界利益の考え方もレクチャーします。
今日も経営カレッジをやっていきたいと思います。
ガイアックスの上田です。
ガイアックス新卒1年目のアカネです。
同じくガイアックスでインターンをしている 大学3年生のレオです。
よろしくお願いします。
今日は、これまでPLとかBSを やってきましたけれども、損益分岐点について説明したいと思います。
ここはあまり難しくなくて、PLのところだけフォーカスして イメージしてもらえたらと思っています。
損益分岐点、よく言われるのが、
損益分岐点、固定費が小さい場合
こういった図なのですが、ここで言う損益分岐点というのは、どこになるか分かりますか? この図を読み取って。
損益分岐点は売上と固定費+変動費の接点。
はい、そうですね。
例えばレストランのお仕事だったら、それぞれ固定費と変動費というのは 例えば何になりますか?
固定費がお店の家賃だったり、変動費が食材の原価だったりと思います。
そうですね。では、例えば、働いてくださっているアルバイトの方は どっちですか?
固定費ですかね。
辞めたりするので変動費じゃないですか。 辞めたり入ってきたりするので。
そうですね。売上が下がると 出勤しなくていいよ みたいな事もありえますし、例えば、一瞬皿洗いで人が欲しいからと言って呼んだ タイミーさんとかは、変動費よりですよね。
ビジネスモデルにもよるので、どこまでが固定費でどこまでが変動費か わからないんですけれども、そこら辺はビジネスによって 若干変わると言う事です。
では、続いて、また別の図を出しますけれども、
損益分岐点、固定費が大きい場合
さっきの図と比べて どう違いますか?レオさん。
固定費が上がった。
はい。そして変動費は?
変動費が下がりました。
そうですね。
今更ですけれど 図の説明ですけれど、右側と上が両方売り上げです。
なので売り上げは0からスタートして 右上に伸びています。
その時にそれぞれ費用がどれ位なのかが 左のメモリで、固定費が結構上の方にあって、変動費は売り上げの伸びに対して それほど伸びていませんよっていうビジネスです。
この2つを並べてみて考えて欲しいのですが、
損益分岐点のコントロールの方法
それぞれどういうビジネスがAで どういうビジネスがBだと思います?
Aは固定費が低いので 例えば店舗を持っていなかったりとか
はい。
インターネットビジネスだったり というイメージがあります。
具体的に言うと店舗を持ってないとか、インターネットビジネスという 例えはどうなのですか?
例えばFacebookとかは、サーバー維持費とかが 固定費になると思うんですけれど、それはすごく少ないのかなと思います。
なるほど。
店舗を持ってないと言うと例えば?
どういう質問ですか?
Aは店舗を持ってないとか っていうので言っていたのですけれど、店舗を持っていない=インターネットビジネス って事ですか?
ちょっと今パッと思い浮かばないです。
ではレオさん、どうですか?AとかBとか、こういうビジネスはこうじゃないかって
僕もアカネさんと同じで、Aは店舗を持たないインターネットビジネス とかかなと思ったんですけど、Bは固定費が高くて変動費が少ないので、飲食店とかかなって。 わからないです。
飲食店は場所を借りてるので 固定費が高いかもしれないです。
じゃあタクシーはどっちですか?タクシー会社。
タクシー会社は タクシーを減価償却じゃないですけど、もう買い切っているんだったら Aになるのかなと思いました。
そうですね。
ドライバーさんの給料形態にもよるんですけれども、結構歩合の比率が高いケースが多くて、そうなればなるほどAに近づいてきますよね。
では、例えば映画館はどっちですか?
Bじゃないですか?
なぜですか?
スクリーンとか音響とか、映画館自体のその設備などから考えて 固定費はかなり高いんじゃないかなって
そうですね。
映画館とかテーマパークとかは運営コストが高いので、デフォルトの、客が100人来ようが1000人来ようが、そんなに原価率は変わらないので。 Bですね。
では、インターネットビジネス、インターネットビジネスと言っても 種類が多すぎるので何とも言えないんですけれども、インターネットビジネスのメディア事業、これはAかBか?
Aじゃないですか?
理由は?さっきの通り?
メディア事業は 固定費があまりかからないイメージがあります。
じゃあ逆に言うと原価は?
原価で言うと記事を作っていく メディアを作っていくための人件費とか
そうですね、では、売上が10倍になると 原価は何倍位になりそうですか?
売り上げが10倍になると原価は1/10倍ですか? だいたい1/8・・・
売り上げが20で原価が10で、売り上げが200に10倍伸びたら 原価はどうなると思いますか?
10/200なので
つまり原価は変わらないということですか?
でも、原価も変わります。
例えば、焼き芋を500円で仕入れて 1000円で売っています。
売り上げが1万円になったら、原価はどれぐらいに膨れ上がります?
それと同じように 同じ割合で膨らみます。
1000円で500円が1万円になったら5000円ちょっと、非常に原価率が高くてって言うか 原価率が存在して、売上が伸びても丸々利益にはなりません。
一方インターネットのメディア事業は?
メディア事業は 指数関数的に割合は減っていく。
つまり売り上げが伸びても原価は伸びない。
原価は伸びないことが多いと思います。
そうですよね だから費用は変わらないですよね。
売上が伸びたところで。 とすると、Aが近い?Bが近い?
Bですか。
そうですね、Bですね。
サーバー代が非常に低い、サーバー代というのはどちらかと言うと変動費ですし、アクセスが10倍になったからといって、利益に与える影響は微々たるものだというのは事実で、そうなるとBです。 では、もうちょっといきたいと思います。
映画館がBなんですけれど、映画館はすごく儲かると思いますか?
もしくはテーマパークはBなんですけれど、テーマパークはすごく儲かると思いますか?
ちなみにインターネットビジネスは、Bのケースが多いですけれども、儲かり始めるとシャレにならないぐらい儲かります。
例えば人材派遣業。 これはAか?Bか?
Aですかね。
Aですね。なぜですか?
人材派遣は人数を増やせば増やすほど、売り上げも上がっていく仕組みなので、変動費が売上に併せて 上がっていくと思います。
そうですね。 つまり、人材派遣業は、すごく儲かるっていうことはありえないですよね。
例えば売上が100が1万になりました。
1万で4000利益を出しています。 こんなことはありえないわけです。
一方インターネットビジネスはそんなことはなくて、売上が爆増すれば利益も爆増するって言う。 傾向的にはそういう傾向にありますよね。
小売り。 店頭でパンを売っていますっていうビジネスと、パンのレストランをやっています。
どちらがAで、どちらがBですか?
この2つで見比べると
レストランがBで小売がAだと思います。 レストランにも固定費が・・・
この2つで見比べると、より小売りの方がAですね。
もうちょっと別の言い方をすると、氷の方が大成功した時に、すごく儲かるっていうことは 実現が難しいっていうことです。
競争原理があるので どれも同じぐらいのリスクはあるとは言え、勝った時にすごく儲かるのはBなんですね。
図を見たら分かりますけど、右に伸びれば伸びるほど、利益が、差が爆増していくっていう、先ほどの質問に戻りますけど、映画館Bですね。 すごく儲かりますか?
映画館は 収容できる最大人数が決まっている。
売上の最大が大体決まってしまっていて、かつ固定費も高いので すごく儲かるっていうイメージはないです。
そうですね。
インターネットビジネスはBで且つ 青天井ですごく儲かるんですけれども、一般的に言われる装置産業とか、箱物ビジネスと言われるものは Bだけれども、上限が決まっているので、儲けも限界があるって言う、そういう意味ではなかなかコントロールが 難しいビジネスカテゴリだと思います。
では続いて、経営をしていて、AっぽくするかBっぽくするかっていうのは、コントローラブルといえば コントローラブルなんです。
例えば正社員を採用する、もしくは派遣社員とかタイミーを使って 人不足の時に対応する。
どちらがAっぽくって、どちらがBっぽいですか?
正社員がBで派遣とタイミーなどがA。
そうですね。一回採用した人が ずっと会社に居ついてくれるのだったら、採用コストもかからないし 周辺コストもかからないので、トータルコストは安いですけれど、一方、業者を使って 派遣社員とかに来てもらうというのは、単価がすごくアップするので、ただ一方で売上の増減に応じて、すいません、ちょっと派遣の皆さん、今月でおしまいです というコントロールはしやすい、という意味では すごく変動費化されていると言う事ですね。
では、事業初期において、AっぽくするべきかBっぽくするべきか どっちですか?
最初はAっぽくして、途中からBっぽくする みたいなイメージです。
そうですね、それはなぜですか?
最初は売上が上がるまでは、固定費を抑えないと利益が出ないので、ひとまずは固定費を抑えて、でも、途中からはできるだけ原価率を 原価率と言うか、原価を抑えたいので Bに近づけると思います。
そうですね。
特にベンチャービジネスにおいては、極端にそういうコントロールを すべきだと思います。
と言うのはビジネスが 本当に立ち上がるかどうか怪しいので。
究極的に言えば、変動費が売上に対して、100%を超えていても全然問題ないです。
固定費が安ければ。
例えば1万とか10万の売り上げを目指していて、今月の売り上げ見込みは100ですと。
仕入れが200円かかっても 全然大丈夫なんです、100に対して。
なぜですか?200円で仕入れて100円でしか 売れないなんてお話にならないですよね。
でも、それでもいいんです。なぜですか?
わからないです。
絶対的な赤字がたかだか100なので、これが1万の売り上げで2万の仕入れだったら、ダメージとしては大きくなってくるのですが、もう少し違う言い方をすると、実際のビジネスを立ち上げた時に、100万、200万の売り上げを確保するのに、300万、400万の仕入れがかかっても問題ないです。
問題は1億とか5億とか 10億の売り上げになった時に、いかに原価を抑えられるかっていうのが重要なので、ただ、それとこれとはまた別の時代の話なので、問題はこの事業が立ち上がるかどうか わからないのに、原価率を下げて利益率を上げようなんていう努力に、時間を割く方が無駄なんです。
そんなことは気にせずに ともかく固定費を下げて、仕入れが高くてもいいので、ビジネスを走らせて、で、売り上げが伸びてきたら、はじめて変動費のことを考える始めるのが 正しい順番だと思います。
では、続いて、
何が固定費?何が変動費?
何が固定費で、何が変動費なのか、ということをもっと整理したいんですけれども、これは非常に曖昧と言えば曖昧です。
これまでPLをやってきたと思うんですけれども、では、レオさん PLをざっと上からイメージつきますか?
売上、総利益、営業利益、経常利益、 税前当期純利益、当期純利益です。
そうですね。最初の営業利益までの3つ、売上と総利益と営業利益、もしくは売上原価総利益、販管費、営業利益。 この5つにおいて、もしくは更に明細に入ってもいいですけれど、固定費と変動費と原価と販管費って どういう関係にあると思います?
売上から原価を引いたものが総利益とか そういう話じゃなくてですか?
PLはそういう話ですよね。
はい
それはそれでPL上は事実です。
一方でビジネスをやっていくにあたって、どれが固定費でどれが変動費なのか と言うことに注目しないと、ビジネスのコントロールがし難いんですよね。
そういう中でPLの内どの項目が固定費で、どの項目が変動費ですか?
原価は変動費。販管費は固定費ですか。
アカネさんどうですか?
私も同じイメージです。
そうですね。 大体のイメージとしてはその通りです。
ただ、売上の中でコストがアップするのが変動費で、コストがアップしないのが固定費なので、別の言い方をするとケースバイケース でもあるということです。
例えば原価なんだけど固定費のものとは例えば何ですか?
価値がが変わらないもの。 例えば機械とかですかね。
そうですね、機械の運用コストが 原価に当てはまる場合はそうでしょうね。
アカネさん他どうですか?
例えばタレントビジネスをしている時の、その人件費っていうのは変動費なんですか?
タレントビジネスというのは 例えば芸能界とかでですか?
そうですね。
タレントさんに固定報酬を 払ってると 固定費でしょうね。
そういう時は固定費です。且つ原価です。
さっき、おっしゃってた通りです。
原価が傾向として変動費で、販管費が傾向として固定費ではあるんですが、必ずしも一致してるわけではなくて ケースバイケースで、要は売り上げが伸びたら変動費で、売り上げが伸びた時に 費用がアップするのが変動費で、売り上げが伸びても 費用がアップしないのが固定費なので、その損益分岐点を超えるためには、どうしたらいいのかっていう時に、固定費と変動費を分けて、売上がいくらになったら、突破できるのかっていうようなシュミレーションは よくやるんですけれども、簡易的には原価を変動費にしても いいんですけれども、実際には中をよく見てそれぞれ固定費と変動費を 分けて考えていかなければいけないです。
では、最後に、
限界利益とは?
限界利益についてお話したいと思います。
限界利益というのは、限界という単語は 会計の世界によく出てくるのですが、一番最後の部分から更に 1売り上げが増えた時に、いくら利益が増えますかという話です。
例えば、ある店がまわっています。
一定程度の規模になっています。
1売り上げが増えると利益はいくら増えるか?
これは先ほどの固定費とか変動費とか 売上という単語を使って、どういう風に算出されると思います?
売上から変動費を引くですかね?
そうですね 売り上げから変動費を引いたものが限界利益、そして、それが限界利益率です。
これはビジネスとかやっていて、例えば売り上げが100の時に、固定費が30で 変動費が30だとして、営業利益率が40%だとしても、新規で1売るのに、例えば、半額にしてくれと言われて、売るべきか売らないべきか これはどう思います?
固定費が結構高いので、半額で売ってしまうと あまり利益が出ないと思います。
そうですよね では、レオさんどうですか?
僕も同じ意見です。
固定費あるのに半額で売ったら まずいだろうって言う。
限界利益率。 わからないです。
ごめんなさい。 数字もう一度聞いてもいいですか?
例えば、売上が1000万で、固定費が300万、変動費が300万の状態です。
で、新規の売り上げ1万円の時の 限界利益率はいくらですか?
利益が40ですね。
そうですね。では、レオさん。
わからないです。
売上1千万の時に300万の変動費と、300万の固定費ということは、変動費の比率が30%、売上に対して30%変動費がかかります。
固定費は300万かかっています。
30%は結果として30%なだけであって、固定費は常に300万なんですね。 だって固定費だから。
限界利益率はいくらかと言われると、さっき、限界利益率の算出方法覚えています?
変動費÷売り上げ?
1-変動費ですよね。
1-変動費率
はい。 1売り上げると0.7利益が出ますよね。
限界利益率は70%ということですね。
今のところで よくわからなかった所はどこですか?
お二人から
限界利益の算出方法 1-変動費はわかったんですけれど、固定費は完全に度外視して大丈夫なんですか?
そこがポイントなんですよ。
今日時点で1000万の売り上げで、300万の固定費で30%の変動比率で、結果的に1000万の売り上げで 400万儲かっています。
営業利益率は40%です。
これで定価から7割引の商品を売っても 利益は出ないですけれど、50%引きの商品を売ると 利益はどうなると思います?
出ますね。
そうなんですよね。利益を生む。そうですね。
利益がいくら出るかと言うのは難しいんですけれど、30のものを50で売るので、40%の利益率が、それでも出るんですね。
もちろんビジネスをやっている中で、あの客は50で、なぜ割引で売っているの?
俺ら正価で買っているのに、そんなに割引きするんだったら 俺にも割引しろよみたいなことになるので、なかなか表立って割引ができないですけれども、実際は変動費を上回る金額であれば、売りたいなと思っているのが現実ですよね。
例えば最近コロナで、ガイアックスの取引先であるユニットさんが、海外から帰ってきた旅行者が、2週間隔離しないといけませんと。
さあ、ホテルからはどれぐらいで仕入れて、そして旅行者にどれぐらいで売れるかって、どんなイメージを持ちますか?
2週間の隔離パッケージです。
空港までの送迎はユニットで行います。
ホテルにお金を払って部屋を仕入れて、旅行者の方に販売する。
そのパッケージが いくら位になるかって話ですか?
そうですね。
ホテルは変動費率は高いですか?低いですか?
変動費率は低いですね。
低いですよね。例えば、1万円の1部屋、1万円、変動費はどれくらいだと思います? では、アカネさん。
水道代と光熱費とかくらいしか わからないので、ほとんどないんじゃないですか。
そうですね。その通りです。
強いて言うと清掃代が高くて、1部屋1000円とか2000円くらいの相場だった と思います。
と言うことは、究極的に言えば、コロナで全くホテルが稼働しない中で、変動費を上回る金額 5割引だとか6割引だろうとかで、仕入れられる可能性があるってことです。
ましてやその金額を表に出すっていうのは、ホテルとしても正価で売りたい気持ちもあるので、なかなか表には出しづらいですけれども、例えば隔離パッケージということで、別で卸させてもらえるっていうのであれば、金額の調整値は非常に高いということです。
もう少し別の言い方をすると、ホテルをパッと見た時に、これはいくらでも値段を落とす交渉ができると 感じられることが重要ですよね。
最後、全体を通して何か質問などあれば。 大丈夫でしょうか?
例えばガイアックスの固定費とかって 何でしょう?
ガイアックスの固定費は 結構、ベンチャーキャピタル的な事業のように見えて、実際は若い人をいっぱい採用して、ももちろんそこでご活躍頂くのですが、半分はその人に将来 事業をカーブアウトしてもらうか、起業家になってもらいたいと思っているので、そういう意味では、そのビジネスモデルを見ると 原価率は高いです。
社員さんですね。
そしてリターンが返ってくるのも先過ぎて、本当にこの人が起業するかどうかもわからないし、起業して成功するかもわからないし、その時にガイアックスが 有利に出資できるかどうかもわからないし、そしてその会社が上場して 我々キャピタルゲインがとれるかわからないという、なので、普通のベンチャーキャピタルならば、本当に見込みのある会社に出会って、出資をするまで費用はかからないですけど、我々はどちらかと言うと、そういった人を採用して給料を払うというところで、固定費がすごくかかっている感じです。
もちろん仕事をしてくださっているので、そのレベルで黒字になっているケースも 多々あるのですが、印象としてはそこで黒字化 しなければならないというつもりもなく、例えば西村たまきさんが、箱根の芸者ショーの責任者で 私が切り盛りしますって言われたら、これは、損出るかもしれないけれども まぁ、巡り巡っていいかって言って、がんばってよ!って言って費用覚悟で サポートするみたいな。そういう感じです。
なるほど
あまり変動費固定費の話をするには フィットしない会社かもしれないですね。
そうですね。なるほど。
他は?
具体的にどのタイミングで、固定費の割合を調整していくのか というところを聞きたいです。
もちろん現金の状況を睨みながらではあるんですが、ベンチャービジネスで言うならば、シリーズAと呼ばれるところで ビジネスが成り立ってますよね、っていう説明ができないといけないんです。
イメージとしては時価総額10億くらい。
その時の売り上げ、月商が正直1000万いってなくてもいいと思います。
500万から1000万位の売上水準にしたら十分、それでプレ10億位でシリーズAと言う 正式なファィナンスがスタートするのですが、それまではどういうお金で回しているかと言うと、エンジェルとかアクセラレータとか、うちみたいなスタートアップスタジオが お金を出しています。
そういったエンジェルとか 我々スタートアップスタジオと言うのは、半分目をつぶって出しているんです。 面白そうね!みたいな。わかった!って言って、ビジネス性があるかどうか と言うのはまだわからないよね、みたいな。
そういうことで金を出します。
そこにおいては 原価率を売上を下回る必要性はありません。
売り上げが1000万位になると 原価がこうなることが可能だと、思いますって言う日本語で我々は許容して、赤字分のお金を出します。
ただ、赤字分のお金を出しますと言っても さっき言った通り、売上規模は低いので大した赤字じゃないです。
2-3000万調達しておけば 半年位やっていけるかな、みたいな。
ベンチャービジネスにおいてはそんな感じです。
どうですか?イメージつきます?
具体的に その固定費を上げていくにあたって、まず何をするんだろうみたいなところって
例えばレクチャー動画を作って YouTubeで配信するには、今後増えてくるとふんで、レクチャー動画を 例えば50回のレクチャーを制作する代行をします。
売り上げ1本20万で50本で1000万です。
これを最初アウトソーシングとかに出すと、1000万じゃ作れません。
2000万3000万かかるかなって感じがします。
それでもそれでビジネスを始めてもいいです。
こうやれば案件が来るっていうのが出てきたり、こうすれば動画が作れるというのが出てきたり、案件が毎月2本3本取れるようになってきたら、正社員を配備してソフトウェアを作って、文字起こしのツールをこうすれば これぐらいコストが下がっていくよね、っていうのが見えてさえいればいいと言うか 見えるようにしておけば、無理して今、その体制作りに 一生懸命頑張らなくていい、そんな事よりもマーケットがあるのかどうかとか、どうやって受注できるのかとか、何を売ればどうささるのか そちらの方が重要です。
実は原価を下げるものといえば 変動費を固定費に切り替えるというのは、我々は精度高くコントロールできます。
例えばタイニーピースキッチンが レストランをやっていて、変動費が高いやり方っていうのは、カット済み野菜を仕入れるってことです。
固定費を上げて変動費を下げるには、レストランの中にキャベツ切りマシーンを買って、ボタン1個押せばキャベツが切れるっていう状態に。
ボリュームが増えないと採算が合わないのですが、これをすれば どれくらいコストが下がるとかっていうのは、すごく高い精度で見積もれます。
すごく高い精度と言うのは2-3割ブレるかも しれないけれどそれ位の精度です。
一方、売上サイドってそんな精度ではないです。
僕らはいろんな企業のベンチャー投資を していますけど、社長が間違いなく売上10倍いきますよって言って、1年後にふたを開けてみたら 1.1倍でしたということはザラにあります。
そのブレの度合いから比べると、その変動費を固定費化する予想のブレなどは たかが知れていて、そういう感じです。
ありがとうございます。
では、今日は以上で終わりたいと思います。
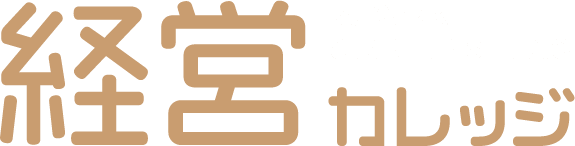







Comments (0)