
会計応用 (4) 企業会計の種類や原則 – 覚えるべき会計基礎ルール
会計の種類についての動画です。財務会計、税務会計、社内管理のための財務諸表など、目的によって使い分ける際の特徴をお話ししています。また、売上を計上する際に、発生主義と実現主義、現金主義それぞれの特徴をレクチャーします。
目次
経営カレッジです。
今日もちょっと 勉強いろいろしていければと思います、ガイアックスの上田です。 よろしくお願いします。
ガイアックス新卒1年目のアカネです。 お願いします。
同じくガイアックスで インターンをしている大学3年生のレオです。
よろしくお願いします。
はい、では、今日は会計について、
企業会計の種類や原則
どんな種類があるのかと言うのと、それに会計を作っていくための いろいろな原則があるので、このあたりを基礎知識として、頭に入れておいて欲しいと思います。
やっぱりここら辺は、今までBSとかBLとかCFとか やってきましたけれども、その前提になったり そもそものところになるので、これぐらいの知識、すごく原則の中でも いくつかしかピックアップしないし、当たり前のところだけですが、ちょっと頭に入れておいて欲しい と思っています。
企業会計の種類
まず最初に企業会計。
会計、どんな種類があると思いますか?
これまでにも少し議題にはあがりましたが。
前回勉強した連結会計とかですかね。
そうですね。 連結会計みたいな種類もあるんですが、普通に作るのが財務会計 と呼ばれるやつです。
それ以外に税務 税金を計算するためのものがあって、それが税務会計と言う風に呼ばれています。
あと、ガイアックスでもそうですし、もしかしたら各事業部にも そうかもしれないんですが、社内の業績管理用の会計を 独自に作っている時があって、それが管理用の会計ということで、管理会計と呼ばれています。
具体的な会計の例
で、この3つは全く同じ数字 になるかと言うとそんなことはなくて、それぞれの背景に応じて、別の数字が出て来ることがあると いうことになっています。
まずは一般的な財務会計からですけれど、
財務会計とは?
株主総会とか決算報告とか、もしくはお金を借りる時に 提出する帳簿、会計になります。
特徴としては 一般的にはディフェンシブには作られます。
特に上場していると 監査法人という方々が入ってきて、この決算が合っているかどうかということ、監査法人さんのOKを取らないと 開示できないんですよね。
で、その時に経営者としては 数字を上げようという、結構、売上利益を頑張って多めに 計上しようと操作しがちですけれども、監査法人がそれダメですよ というやり取りをして、結果的に出てくるものになるので、結構、利益に関しては ディフェンシブになっている、と。
上場していないと どんなチェック機構があるのかと言うと、取締役会で、とか 監査役が、とかってあるかもしれないけれど、一般的に上場しないと 取締役も監査役も身内だったりするので、ほとんどチェック機能がなくて、税理士さんに見てもらっていたら、税理士さんがある程度無茶なことは ストップしてくるかもしれないけれど、税理士さんも年間20万とか30万 しか払ってないような会社になると、月2万で税理士さんが 実地調査なんかするわけなくて、本当にちょっとしたデスクワークで するくらいの金額になるので、自由に作れちゃうわけですよね。
結果的に無茶苦茶な決算にもできるし、積極的に粉飾を紛れ込ました決算 にもできるし、場合によれば お金をどうしても借りたいと思えば、銀行用に提出する決算は あたかも数字がいいような決算になるように、決算書を作ることもできるし というような感じになっています。
税務会計とは?
続いて税務会計です。
これは税金の計算で作るものになります。
これ、なぜディフェンシブにできない、管理会計と違ってディフェンシブではないのか っていうのはわかりますか?
減価償却を勉強した時に 税を一定以上納めないといけないから、償却を1年に一気にするんじゃなくて、ちょっとずつみたいなことを 話しがあったと思うんですけれど、それと同じで税を納めるために 多めに計上するのかなと思っています。
そうですね。税を納めるために利益を 少なめにすることは許されないと言う事ですね。
無理に多めにかけとは言われませんけれど。
では、この税務会計のチェック機構は どうなっていると思います?
税務署の方ですかね?
そうですね。税務署の方がチェックする。
税務署はどういうところを どういうような会社、どういうようなタイミング どういう風にチェックしてくると思います?
年末にチェックすると思うんですけど、大会社もそうだし 上場してない会社もチェックすると思います。
そうですね。
まず小さい会社は あんまりチェックされないんですね。
税務署のスタッフの皆様方も 税金で動いているので、(人日)5万の人間が動いて 1万税金多く取れました。
とかって言ってもしょうがないので、もちろん建前的にはそんなことは 言わないと思いますけれど、現実的にはめちゃくちゃ儲かってそうなのに、税金の申告が少ないなっていうところを 徹底的にやっていきます。
で、もちろん上場企業でも 税金が間違っているケースもあるので、もしくは上場企業でも タックスプランニングと言うか、節税と言うか 脱税ではないんですけど、やっぱり頭の良い人達がたくさん集まって、いかに税金の隙間をくぐり抜けて、なんとか税金を納める事を 減らせられるかと言う事を頑張るので、そういったところをチェックしに来ます。
ただ、上場企業のそういうテクニカルに、税金を減らそうとしている人達の対応と、そもそも帳簿をちょっとちょろまかして 税金減らそうみたいな、そういうものとでは全然チェックの仕方が 違うとは思うんですけれどね。
で、税金に関しては時効がありまして、確か、5年、3年じゃなくて 確か5年だったと思うんですけれど、時効が来るとおしまいなので、見に来たら5年分チェックされることが 多いです。
6年前税金これ少なく払ってた って言ったって時効で僕ら逃げられるので。
で、どれくらいの頻度で来るかってことは、てことは、5年に1回くらいのペースで 来かねないって事なんですけれど、やっぱり会社によりけりで、例えば、上場していても決算書が明らか、明らか、決算書が正しいのはおそらく 一定程度、担保されているので、明らかにこれ儲かってないな、と、で、決算書はきっと正しいよな、と、もしかしたら儲かってなくても、払わなければならない税金も あったりするので、そこら辺をちょっと誤魔化して いるんじゃないかって言って、チェック入るかもしれないですけれど、そういうところは あんまり積極的には来ないですね。
で、やっぱり明らかに儲かってそうなのに、申告が少なそうだなぁ、みたいな、例えば、現金商売とかの方が 誤魔化し易いんですね、傾向的には。
企業と入出金やって 銀行口座を通していたら、税務署って銀行から情報提供とかを 受ける事は可能なので。
そういったところで誤魔化すのは なかなか難しいので。
現金商売で且つ 領収書を取ってないような会社、領収書を払わないような会社の方が、売上の調整がしやすい かもしれないですね。
一般的な会社は 株主さんは自分だけだったりするので、財務会計というより年間1回、中小企業だと 年間1回税務会計用の決算締めて、それをベースに財務会計にも活用して、で、それでお終いっていうことが 多いは多いです。
管理会計とは?
続いてあるのは管理会計。
これは自分の会社の中の数字を 管理する用の会計なので、管理会計というほど 固まったものがあるわけじゃなくて、まあ自由に作ってください、みたいな そういう感じのものです。
例えばガイアックスでも バジェットと、予算ですね。
で、リザルト、その結果と、フォアキャスト、その予想っていうのを、常にこの3つを更新、特に予想の方を 全社員が常に更新するような、バジェットとリザルトとフォアキャストを 見比べるっていうことは、月単位じゃなくて日単位でやっていると 思うんですけれども、全事業部が。
それで各事業部で 20事業部くらいあると思うんですけれど。
その月次のそのフォアキャストとかを、その予測とかを管理していくのに、会計ルールに基づいた会計とかやっていると、いろいろな点でやってられないんですね。
例えば、経理の人が仕事している費用を、各事業部に割り振るとかっていうのは、めちゃくちゃ難しいわけですよ。
ガイアックス全体で経理の人の人件費 っていうのは出て来ますけれど、じゃあ、TABICAをやっている TABICA事業部の分の経理の費用って、いくらだったっけって計算し始めると ゾーっとするわけですよね。
しかも本来、税務会計的には年に1回、財務会計的には うちは上場しているので四半期に1回、取りまとめればいいものを、月次単位でまとめるとなると、月次単位でそんな細かい計算を いちいちやってられないんですよね。
そこでうちの会社は、じゃあ、そういった管理系のコストっていうのは、正社員が1人いればきっと いろいろもろもろコストがかかっているから、12万かな?12万管理部に払ってください、と。
で、正社員以外の 契約社員さんとか派遣社員さんとか、業務委託の方とかインターンの人とか だったら1人当たり2万円、管理部に払ってください、と。
で、それでちょっと 間違っているかもしれないけれど、ザックリ数字わかるよね、みたいな、そういうようなルールで、例えば、管理系のコストのところは 処理しているわけです。
他にも例えば 全社として金を借りているけれども、事業部として、じゃあ その金を借りてる金利が幾らになるのか、っていうのを計算するのは すごく面倒臭いですよね。
そういう意味ではそれも事業部のバランスシート、それぞれ作っているとしたら そのバランスシートに、一定の金利的なもの5%をかけて それが金利ね、みたいな、そうやって簡単に処理するケースもあります。
売上も例えば これも会社によるんでしょうけれど、例えば、開発部と営業部が売上からの粗利は 折半しちゃいます、みたいな、この折半は 正しいルールかどうかわからないけれど、事業部を管理するためには それぐらい社内ルールを適当に作って、適当な決算書を作ればいいだけです。
財務会計とかは科目が、一般的にコンセンサスを得られた科目で 作るんですけれども、例えば、業務委託費だとか、交通費だとか接待交際費みたいな、そういった形で作るんですけれど、この管理会計では別に自分達がわかればいいので、好きな科目で別に作ってもいいです。
ちなにガイアックスは バジェットとかリザルトの管理を、かなり財務会計に近づけているので、正直、事業部からはちょっと 使い勝手が悪いんですけれど、事業部の皆さんも 財務会計に親しむことはできるし、財務会計との連動性が高いので、事業部ごとの管理会計を足し込めば、ほぼほぼ近い財務会計になる という風な形で運用はしています。
ここまで大丈夫ですか?
大丈夫です。
はい。大丈夫です。
では、続いて、
企業会計の種類
会計の原則の話に移りたいと思います。
会計の取引が発生してそれを記帳する、もしくはPLで認識するタイミングって言うのを ちょっと話していきたいと思います。
具体的な認識のタイミング例
PLとBSがありますが、会社経営においてPLっていうのは、どういう位置付けにあると思いますか?
何のためにPLが存在すると思います?
その1年間の期間とかで 業績を明確に知るためですかね。
そのとおりですね。1年間の期間とか一定の期間 月次決算ならば月次決算で、月の中で業績をきっちり把握するために PLというのはあります。
もうひとつは 利益が出ると資本の部に入ってくるわけです。
これ、大丈夫ですか?
資本の部に入って来るってことは 株主さんに配当できるってことなんですね。
つまりPLっていうのは 業績を管理するっていう目的と、実際にそれで出てきた数字をもとに、株主さんに現金を配ることができるっていう、そういう背景が後ろに隠れているわけです。
じゃあ、実際に利益が出ているぞ っていうことをPLで表現するために、いろいろな取引を 管理していくんですけれども、じゃあ、どういう風に いつどこで利益が出たのかっていうことを、記帳するのかっていう考えが こちらに書いてあるものですね。
もうちょっとわかりやすく言うと、売上はいつ計上するんですか? っていう、そういう話です。
現金主義っていうのはお金を頂戴した時に 売上を上げるというやり方なんですが、これはどう思いますか?
その現金が動く時期にズレがあった場合 結構、実態と離れそうだなと思います。
そうですね。 翌月払いでお願いしますって言って、いや、ごめんなさい、2ヵ月後でいですか? しょうがないですねって言った時に、実際の納品活動は今月やっているのに、売上計上が来月になったり 再来月になったりって言って、ずれてくるってことですよね。
PLは作りやすいんですよ。
みなさんは現金主義のPLのシュミレーションと、掛け商売の時、掛け商売って言うか 請求書払いの時のPLの処理を、前回ちょっと勉強したと思うんですけれども、当たり前ですが現金主義の場合は すごく簡単に計算が出来て、銀行通帳見たらわかるっていう、銀行通帳でPLが作れるっていう意味で すごく楽ではあります。
基本的にPLを作るのに、発生主義というのをとられるんですね。
発生というのはその物事が発生した時に 売上計上しますと言う事になるんですけれども、例えばキャベツを仕入れて お店に入れてもらいました、みたいな。
それの支払いが2ヶ月後だろうが、お店に入れてもらってそこから調理に 使えるような状態になった瞬間に、費用認識すべきですよっていう そういう考え方になっています。
それとか3ヶ月間マッサージをしてもらう 契約をしました。
それが前払いだろうが 後払いだろうが、3ヶ月で30万払う契約だとしたら、毎月10万ずつです。
ここまで大丈夫ですか?
はい。
はい。
基本的には発生主義 つまり現金主義と違って、物事が発生しているリアルタイムに計上していく っていうのが基本なんですけれども、売上の認識に関しては もう一段ディフェンシブになっていて、金額が明らかになって返金もしなくて いいですよっていう形の実現、実現するまで売上計上はやめておきましょうね っていう風になっています。
費用の方は、例えば5年間使えそうな車を 買ったら5年で分割するわけです。
例えば3ヶ月のコンサルティング契約を結んで 300万見込んだら、毎月いろいろやってもらってるんですが、300万を3ヶ月で割ったりするわけです、 費用の方は。
売上の方はもちろん納品したら 実現主義的に納品書で、本来は検収書なんですけれど、検収してもらったら 売上が実現した形になるんですけれども、例えば、コンサルティングが入っています。
3ヶ月間やりますけど3ヶ月後に コンサルティングの報告書を提出します。
てなると、毎月売上計上するのは ちょっとアグレッシブで、3ヶ月分のコンサルティングの報告書を出して、向こうが報告書に関して 受領したというタイミングで、初めて過去3ヶ月分の コンサルティング契約の総額を計上できる、という方が よりディフェンシブなわけなんですよね。
そういう意味では発生主義というより、もう一段踏み込んで リスクのない形の所までたどり着けて、初めて売上計上するっていう形の 実現主義になっています。
なので、すごい小さい会社は、現金主義でビジネス記帳してたりするかも しれないですけれど、もうちょっとまともな会社だったら、費用は発生主義、売上は実現主義で 計上することが多々あります。
仮に現金主義で 月次決算していたとしても、年初と年末だけズレを修正して、発生主義、実現主義で年間の決算を出す って事はあり得ると思います。
すごい小さい会社以外は、基本的に発生主義、実現主義で 決算しているんですけれど、時々イレギュラーな形で 現金主義を採用することもあります。
例えば100万円銀行に預けていて 金利が1%です。
で、12月末日に1万円金利が入ってきました。
皆さんの銀行通帳に金利が入っている、記帳したことあります?ないか?
わからないですね。
見たことない?
見たことないと思います。
まぁ、ちょっと金利が低すぎて、そんな大金預けていないから
そうですね。
金利が付く瞬間を 見た事ないかもしれないですけれど、まあ、例えばそんな時に、1万円を月次で割ったり四半期で割ったり しないケースが多いんですよね。
銀行から金利が振り込まれた瞬間をもって、利益計上するってなると、これいわゆる現金主義なわけです。 なんかわかります?
金利を残高の1%で12割して、どうのこうのってするのは面倒臭いので、それとか ガイアックスグループでも1回あったんですが、グループ会社なんですけれど、ASPのサービスやってるんですね。
で、無料でトライアルできるんです。 そこまで大丈夫ですか?
で、無料でトライアルやってもらったって、ガイナックス側にとっては、何も変わりないんですよ。
ネット上にソフトウェアが置いてあって、オンラインサインアップして 勝手に使ってる、みたいな。
グループウェアのサービスなんですけれど、で、ある基準を超えると、フリーミアムって呼ばれるもので、フリーとプレミアムの合体した単語ですけれど、フリーミアムと言うサービス形態で、ある基準を超えるとお金を払ってもらわないと 使えませんよっていう、そういう形になっています、と。
で、ある基準を超えるとお金を 使ってもらわないと困りますっていう時に、お金を払ってから その基準を超えられる方がいいのか、その基準を超えて使えるけれど、超えたら請求とか支払いをしなければならない とかどっちがいいと思いますか、例えば 議事録を100件超えると1万円かかります。
200件超えると2万円かかります、 みたいなサービス。
ASPでやっています。
どういうような課金システム 決済システムにしたらいいと思います?
その会計の事を忘れて ビジネス的に。
先に現金が入ってくる方が いいなと思います。
まあ、そうです。 先に現金が入って来る方がいいですよね。
でも利用者としては、例えば アカネさんが議事録を書いています、と。
さぁアップしようかなと思うと、これ100件になりましたって言われて、ここで議事録を追加するには経理部に言って、これライセンスを買ってもらって、それで初めて議事録をあげるのか ってそういう話になるわけですよね。
月末になるまでどれぐらい使うか わからないわけですよね。
例えば携帯電話もそうなんですけれど、基本的には使い放題で 使った分を後で請求される方が、すみません、もう 料金を払って頂いた分はおしまいです。
ここで1000円払ってから次の電話できます っていうよりも、ビジネス的な売上が上げやすいんですよね。
つまり、現金回収のリスクの少なさで言えば、アカネさんの言って頂いた通りなんですけれど、売上の上げやすさ もしくは利用者の利便性を考えると、後払いの方がいいってことなんですよね。
逆に言うと後払いになると 今アカネさんが言ってくれた通り、現金回収ができていないので 現金回収のリスクが劇的に高まるわけです。
もう倒産しそうな会社もたくさんある中で、今月3万円なりました、って言っても、こんなサービスもういいよ。
ログインもしなくていいわ。 捨ててしまえ、みたいな。
そういうお客さんもいたりするわけで。
こうすると、例えば 現金主義とか、発生&実現主義で言うと、どんなトラブルが来そうな気がします?
発生主義として計上したものの、その後現金が入って来ない っていうことが起きると思います。
そうですね。 実現主義で計上したものの、売上を計上したものの 入って来ない、と。
そうすると売掛金が倒れる。 売掛倒れになって、損金が必要、損金と言うか、営業マンがその出た損を回収する という義務を会社は背負うわけです。
これ、なぜなら 例えば、12月に売上計上したのに、1月末に振り込まれるべきお金が 振り込まれませんでした。
そうすると12月に嘘の売り上げを 立てたのかっていう話になるので、頑張って回収しに行かないと いけないですよね。
もちろん回収できなかったら しょうがないので、1月に損金を出す。 例えば費用を立てればいいんですけれど、12月の決算の信頼性が 失われるわけなんですよね。
もちろん12月って売上立てた時に、過去の売り上げの売掛金の その倒れた率を掛け合わすので、傾向から見込んだ売上しか 立てさせてくれないのですけれど、それでも1回記帳したものは、きっちりとマネジメントしましょうよっていう プレッシャーがすごく高まってくるわけです。
でも話戻って ASPでフリーミアムで、利用者が1000社とか2000社とか3000社いて、そのうち気がつけば ある会社が有料化していく、みたいな。
で、こっちも向こうも 全く管理していない、みたいな。
で、向こうに請求書は自動で送りつけて、3ヶ月お金が振り込まれなければ、サービスが止まるという仕様 にしてるとしたら、もうなんかこれ実現主義でやるの 面倒臭くないですかって話になってくるわけです。
意味わかります?
もう、入金してもらった時に 売上計上しちゃいましょうよ、みたいな。
売掛金も回収しに行くことはありません、と。
3ヶ月で払ってもらえなかったら、もう残念って言ってサービスを止めて お終いになりますって言う。
営業マンがわざわざ電話して、すみません、2月分の3000円なんですが 払ってください、なんていう、連絡する事はないっていう、そこら辺のロジックを きっちり固めることによって、現金主義に仕立てて、会計の安全性も通り っていうようなことはやったことはあります。
かなりイレギュラーですけれどね。
また別の話では 昔ガイアックスが買収した会社が、現金主義で決算作っていたんですね。
で、例えば12月末に買収したんですけれども、実際5月末かなんかなんですけれど、月会費が翌月振込だったんです。
プロバイダーみたいなサービスで、個人会員が3000円、12月分の3000円を1月に払う っていうそういうサービスです。
その会社の12月の売り上げは 何月分の会費でしょうか?
11月ですかね。
そうですね、11月分の会費を 12月に銀行振込顧客がしてきて、現金主義だから 12月に振り込まれたものを、12月の売上と そういう風な記帳をしている会社でした。
で、この会社を買収する ディスカッションをする時に、その決算書で ずっとディスカッションしていたんです。
わかります?
で、12月末日に買収しました。
で、問題は1月に入ってきた現金、これが前のこの会社を売ったオーナーが、いや、この1月に入ってきた現金は 12月分の会費だから俺のものだ、って言って、我々は1月の売上だから 1月度からは我々のものだからそれは我々のものだ、って主張したけれど これどう思います?
うん、難しいですね、どうだろう。
これは12月末に買収したんですよね。
それだったら12月の利益は 向こうが得るべきなのかなあと思います。
まあ、そうかもしれないですよね。 アカネさんはどう思います?
これでもしその現金が入ってくるのが 3ヶ月、2ヶ月後とかの会社だったら、じゃあ今度11月も12月も どっちも入ってこないってなる。
いや、でも私も向こうの会社 買収された方の現金になると思います。
まあこれ15年前ぐらいの話ですし、だいぶ昔の話なんですけれど、契約書に例えば 12月買収までの売上は旧オーナーのもの、それ以降の売上は 当社のものって書いていたとしても、その売上が実現主義的な売上なのかとか、現金主義的に考えた売上なのかとか 一切書いてなかったんですね、契約書に。
で、おそらくM&A契約のたくさんの種類の テンプレートがあると思うんですが、どのテンプレートにも、両方が同じ発生&実現主義で やっているものだと思うので、まさかそこにブレがあるというのは 想定できずですね、契約書を見てもよく分からなかったんですよ。
ただ、ちなみに ガイアックスは実現主義なんですけれど、その対象会社は 現金主義で会計を作っていたので、これが12月の売上だって言うんだったら、過去に出していた決算書は間違っているん じゃないかっていう話を我々は主張して、1月に入金された12月までの月会費は、12月分の月会費だけど 1月の売上ですよね、みたいな。
1月の、なぜなら現金主義である そっちが記帳していて、それで我々は、デューデリして、その対象会社を買ったので そうだって言って。
結論としては 両方が言いたい事を言い合って、もめて、で、先方がちょっと 我々に訴訟されてこられて、で、実は そこから最高裁まで争ったんですけれど、結論としては我々の主張が通って、1月の入金されたものは 1月の売上であり我々のものであると、もちろんガイアックスとしては 連結にした瞬間から、現金主義で作っていた会社を 連結にした瞬間から、実現主義に切り替えているんですけれどね。 会計としては。
うちのグループでは 現金主義なんか許されないので。
まあそんな話もありましたっていう話です。
では今のをちょっと整理し直すと、
現金主義とは?
現金主義はあまり使われず、状況が正しく把握しづらいですよね、と。
発生主義とは?
発生主義って言うのは 主に費用であります、と。
実現主義とは?
実現主義っていうのは引き渡しとか、もう返金しなくていいっていうのが、明確になって初めて実現します と言う感じになっています。
新収益認識基準
はい、では、次の話になりますが、来年2021年4月からですが、大手企業対象に 新収益認識基準と言うのが出てきます。
これちょっと 世の中では話題になっているんですが、これ、どういうことかと言うと、売上計上基準が とは言え曖昧だったんですね。
どういう風に曖昧だっかと言うと、例えば 3年サポート付きのパソコンを売りました。
10万円です。 売上認識はどうしたらいいですか?
クライアントが3年間使って 何も問題がなかった時に、初めて売上計上されるのが 正しいんじゃないですか?
まあ、とも考えられますね。
でも町の電気屋が3年サポート付きの パソコンをレオさんに売っています、と。
売上計上が3年後なんて 信じられないですよね。
そうですね。 規模によりますよね、その会社の。
そうですね。基本的に 一般的に3年サポート付きのパソコンなんて、売った瞬間に売上計上していた と思うんですよね、これまでは。
パソコンならまだ 話はわかりやすいんですけれど、もっとバカでかい工事とか システム開発とかで、同じような形で売っていたとしたら、いや、それは サポートに関する費用を想定して、一旦9万円だけ売上計上して、残り1万円は3年で分割して 売上計上しましょう、みたいな。
そういう風に しっかり物とサービスを分離して、管理していきましょうって言うのが 新収益認識の方法になっています。
大手企業対象だけなので 中小企業は関係ないのですが。
はい、じゃあ以上で 説明終わりたいと思います。
本日はこれで終わりたいと思います。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
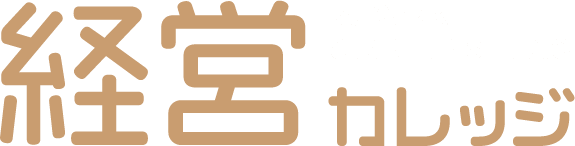














Comments (0)